活動紹介
■ 稲武と養蚕業の歴史
古く奈良時代に始まったとされる稲武の養蚕(『三河養蚕由来記』より)。三河地方は、古来より純白で良質な生糸を産出することで知られ、元々養蚕に適した土地柄なのです。
養蚕を地域の産業振興の一助にしようと考えたのが、稲橋村(旧稲武町は、稲橋村と武節村が合併して誕生)の豪農、古橋家六代目の古橋源六郎暉皃(てるのり)でした。明治8年に桑苗を買って各村に配布して栽培を奨励し、稲武の地における養蚕発展の礎を築いたのです。
その後、稲武の養蚕業は隆盛。明治15年(1882)に伊勢神宮への神御衣献糸(神御衣祭に供えられる和妙の原料の生糸の献納)が始まり、以来今日に至るまでこの奉納は、140年以上続いています。また、大正天皇の大嘗祭(即位礼)には繭を調進しています。
…しかし、時代は移ろいます。
稲武では最盛期には500戸が養蚕を営んでいましたが、経済発展に伴い稲武から都市部へ人口が流出すると共に、化学繊維の台頭や安価な外国産繭の流入で養蚕家は減少の一途。遂には、3戸にまで減ってしまいました。
そんな折、宮内庁掌典職からの依頼を受けて、平成度の大嘗祭で重要なお供えものである繒服(にぎたえ/絹織物)を、稲武から調進することになりました。ちなみに、大嘗祭で最も重要なお供えものであるお米は亀卜によって斎田が決まり、繒服(にぎたえ)は稲武地区(現愛知県豊田市)から、麁服(あらたえ/麻織物)は徳島県の木屋平村からとなっており、とても名誉なことなのです。
この繒服の調進を一つの契機として、稲武を「蚕の里」として蘇らせようという気運が高まりました。そして有志が集まり、「まゆっこクラブ(いなぶまゆっこ)」を結成。その伝統ある歴史を誇りを胸に、日々養蚕スキルの伝承と絹を用いた作品づくりに励んでいます。
■ 養蚕の魅力を伝えるのも「いなぶまゆっこクラブ」の役割
養蚕の魅力を少しでも多くの人に分かっていただきたい。そんな思いで、まゆっこのメンバー達は、稲武にとどまらず、都市部でのイベントにも積極的に参加しています。地元稲武の「ふれあい祭り」や、豊田市の「ものづくりなぜなぜプロジェクト」、名古屋祭りなど各地のイベントに出店、繭やシルクで作った作品を展示販売すると共に、クラフト製作の体験教室を随時開催しています。


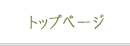
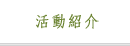
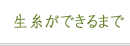
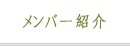
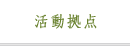

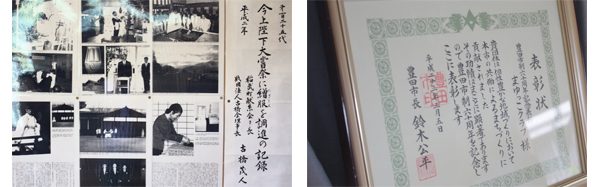


最近のコメント